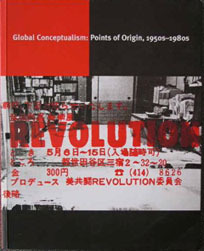斎藤義重 [アート論]
斉藤義重は一九〇四年生まれで、二〇〇一年に九七歳で亡くなった日本の現代美術家です。
青森県広前市生まれ。父親は陸軍大佐で、高級官僚軍人で、海外への留学経験もあり、裕福な西洋式の生活をしていたようです(出典モリヤ)。父の任地変更で東京の新宿に転居して牛込尋常小学校に入学。尋常小学校を卒業後、父親のすすめで、日本主義思想家の杉浦重剛が校長を勤める日本中学に入学しています。
杉浦重剛というのは、三宅雪嶺、志賀重昂らと政教社発行の「日本人」の刊行に力を尽くし、大正時代の国粋主義的な思想家であり教育家でありました。
斉藤義重は、しかし日本趣味の少年ではなくて、お気に入りの映画は「チャンバラ映画」ではなくて、「マルクス兄弟」や無表情の「バスター・キートン」らのドタバタ喜劇であったのです。キートンは「The Great Stone Face(偉大なる無表情)」というニックネームがつけられ、他にも当時から「すっぱい顔」「死人の無表情」「凍り付いた顔」「悲劇的なマスク」といわれましたが、このキートンという存在と、斎藤義重の関連性は、《もの派》の形成に影響を与える面までを持つ重要なもののように思われます。
同じ喜劇映画でもチャップリンではなくて、キートンであるところが、斎藤義重の特徴と言えるように筆者は思えるのです。
キートンは喜怒哀楽を表情に出さず、無表情の紋きり顔で、急斜面を転がり落ちたり、列車の上を全速力で駆け抜けたりするなど、非常にアクロバティック命がけのドタバタのアクションを展開したのですが、斎藤義重もまた、作品においても、モダンデザインにある空無性に通ずる紋きり的で、喜怒哀楽性をはじめとする個人の感覚や感性のニュアンスを欠いた、無表情で、空無的な作品を追究した美術家であったのです。
正確に言えば、そうした無表情な空無性を、芸術性と考えた人だったのです。それは宗教を否定した科学の時代と言う近代の根底にあるものといえます。
この日本中学から陸軍幼年学校を受験するのですが、合格で来ませんでした。喜劇映画を見すぎたのかもしれません。つまり軍隊でのエリートコースに乗る事が出来なかったのです。斎藤義重は、次第に反逆的・虚無的意識を培ってゆき、裕福な家庭に生まれたドラ息子として定職にも就かず、体制に批判的なマルキシズムやシュールレアリズム運動の周辺に身を置きながら、熱心な革命運動家にもなりきれず、かといって、職業美術家になろうとする強い意識もなく独自の構成的作品を気の向くままに作るようになっていきます。
軍人の父親を持つ斉藤義重のこの挫折について、三木多門(国立近代美術館学芸員)は、次のように述べています。
「日本中学は日本主義者として知られた杉浦重剛の創立したもので、その学校と軍人の家庭という環境は、早くから美術や文学に心惹かれた敏感な斎藤少年の心に、やがて一貫して持続する一種の反逆精神を植え付けたと思われる。反逆精神はもちろん青少年期に共通したものであるけれども、彼の場合、単なる一時的な、個別的なものでなく、本質的に固定したものから飛躍せずにいられない欲求――前衛精神として、継続し発展して行った。」(1978年の東京国立近代美術館での大規模な斎藤義重展(国立の美術館では初めての現代美術作家の個展)の図録)
三木多門の指摘する、固定したものから飛躍せざるを得ないという斉藤義重の前衛精神というのは、関根伸夫との対話が《もの派》を生み出す大きな触媒、触媒どころか、関根伸夫をも超えて展開する精神の運動として展開して行きます。
それはキートンの無表情な喜劇性にも通ずるものでした。キートンの喜劇性というのは、日常生活を徹底的に破壊するもので、例えば建物が強風で次第に飛ばされて行くシーンなど、映画の特徴がダダイズムに通じるものがありました。
この破壊性はしかし、無声映画時代には威力を発揮するのですが、時代が過ぎてトーキーの時代になると、キートンの人気は落ちていきます。トーキーへへの移行を成功させるチャップリンとキートンの差というのは、実は近代に潜む、大きな亀裂なのです。それは単純な破壊衝動と、もう一つ破壊の後の再度の新たな構成や構築に対する情熱の有無の差なのです。
斎藤義重の生涯を通じて展開される芸術性は、破壊衝動と言っても良いもののように、筆者達には見えるのです。なぜならば斉藤義重が晩年の九〇歳代に至り着いた木を黒塗った彫刻作品は、作品と言うよりは、作品そのものが壊れてような《第十六次元》という崩壊領域の美術表現に至り着いていたからです。
それはピカソがキュビズムを展開してヨーロッパのルネッサンス以来の絵画を解体し、ついには分析的キュビズムと呼ばれる《第十六次元》の崩壊領域に至り、抽象美術の入り口に立った地点に呼応するように見えるものだったからです。このピカソや斎藤義重の芸術にある破壊衝動の運動は、実は《もの派》を生み出す基本衝動だったのです。
斎藤義重の美術作品の出発点としては、一九二〇年、斎藤義重が一六歳の時に、南伝馬町の星製薬会社で開かれたロシア未来派の亡命作家の作品展を見て、その新しさに衝撃を受けたというのが、あります。斎藤はロシア10月革命の混乱を避けて、アメリカに亡命する中継地として日本に滞在していたロシア未来派画家ダヴィード・ブリュークらの作品展を偶然みた時の衝撃を次のように語っています。
「――私は学校の帰り一人で見に出かけたのですが、会場に入るとすでに作品はすっかり展示されてあるけれど、未だ開場前らしくひっそりとしていた。ただ4人ぐらいの画家が、床に絵の具を散らばせて壁の絵に向かって熱心に筆を入れていているのです。私は静かに絵を一巡して眺めましたが、今までに直面したことのない絵画で、驚きと異常な興味を抱かされて、今度は彼らが描いている様を、いつまでも飽かずに見つめていました。―――この未来派作家の絵を理解するには少しあとにならなければならないのですが、彼等が描きながら示したことは。今まで知っていた絵画の他にまったく異なる表現があるんだという発見、扉を開いて何か別の世界を示されたように、生々しい刺激があり、それが深く潜在してしまって、後々まで作用を与えたことは、私にとって一つの出来事であったように思います」(「私と抽象表現」1984年東京都美術館・斎藤義重展図録より)
斎藤義重が見たのは、ロシア未来派なのですが、まず、未来派そのものを理解しておく必要があります。
未来派というのは1909年にイタリアの詩人フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ ( 1876-1944)によって起草された「未来主義創立宣言」がその発端でです。内容は前年に出版されたジョルジュ・ソレルの「暴力論」に影響を受けており、あらゆる破壊的な行動を讚美する非常に過激なものだったのです。つまり斎藤義重が、ロシア未来派展で見たものの中に、こうしたキートンの喜劇とも通ずる破壊衝動のようなものが潜んでいたのではないか、と考えるのです。
斎藤義重の美術の制作は、しかしそれほど順調には展開しません。
一九二五年、二一歳の時、写実的再現性の絵画への嫌悪感や、ロシアの未来派作家達の影響から絵を描くとに行き詰まり、文学への傾斜を深めています。実は、斎藤義重はもともとは美術家というよりも小説家ではないのか?と考えてみるのも一つあり得る者ものなのです。。ひとつの小説を書いたと伝説的に言われているのですが、これは筆者の聞いた伝聞でしかなくて、出典も明記できない者ものですが、次のような小説です。
とある村の村人達が……お互いに食いあって、最後は誰もいなくなった、そういう小説です。一種のニヒリズムですけども、無に至ってしまう、そういうニヒリズムが斎藤の中にもともとあるのです。大正ニヒリズムというものです。 (つづく)
寿命と変態 [生きる方法]