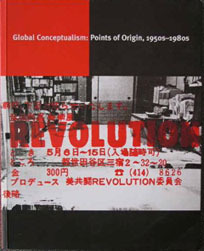2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(5)
おそらくこうしたオーソドックスな調和への視点を逆転させる事で、この越後妻有トリエンナーレのかなりの部分は出来ているのです。つまり調和を避けて、不調和にする事で、芸術という名前は成立していると見えるものが多いということです。不調和にする一つの方法が、ボルタンスキーに見られる廃墟性や、崩壊性です。廃墟や崩壊が、人を引きつけるのは、確かなのですが、しかし崩壊が芸術であるとは言えないのです。もう一つは「ばさら」です。
まず、廃墟性や崩壊性についてみてみましょう。
今回の目玉作家の塩田千晴の作品です。
不調和性というのは、芸術であることを、根拠づけるものなのか?
越後妻有トリエンナーレの目玉の作品のとんど全部はデザイン的エンターテイメント作品であって、私には《真性の芸術》として評価することができません。長谷川裕子が言うように『アートとデザインの遺伝子を組み替える』ことが実際に行われていて、これらの目玉作品の社会的デザイン性が高い事は充分に認めますが、《真性の芸術》性は欠けているのです。

日本文化には、《文明》対《原始世界》という、重要な対立構造が潜在しているのです。外国から高度の人工的な新文明が日本に入ってきて、それを輸入し喜んで学び、支配者たちはこの《輸入文明》、例えば仏教や、あるいは西洋文化を背景にして民衆を支配するのですが、支配される民衆の中には、文明以前の、狩猟採取文化、つまり野蛮な文化が脈々と流れていて、上級の《輸入文明》に対して、常に反抗的な姿勢があるというのです。しかし問題が複雑なのは、反抗的な姿勢が屈折していることです。反抗自体が《輸入文明》に触発され、反発しつつ、にもかかわらず模倣し、なぞりつつ解体し、伝統的な野蛮文化のボキャブラリーの中に還元し、あざ笑うことに表現を見いだしていくという、複雑な摂取と解体の流れがあり、「ばさら」とか「かぶく」とか言われる美意識となります。
「ばさら」「かぶく」という言葉を、辞書でひいてみると次のようにあります。
「ばさら【婆裟羅】室町時代の流行語。①遠慮なくふるまうこと。乱暴。 ②はでに飾り立てて、いばること。だて。③しどけなく乱れること」
「かぶく【傾く】①頭がかたむく。かしぐ。②はでで異様なふるまい・みなりをする。」(日本語大辞典 講談社 1989年)
つまり日本の中には乱暴で、はでに飾り立てて、しどけなく乱れる表現の系譜があるのですが、これが室町時代に「ばさら」とか「かぶく」というような言葉で姿をあらわし、それはしかし不自然なものであり、異様で、派手で、エキセントリックで、《異端の系譜》の源流とも言うべきものになるのです。
これを戦後日本美術に当てはめて、分かりやすく言えば、それは敗戦後の岡本太郎によって唱えられた縄文主義であり、対極主義であり、あのどぎつい派手な色合いの絵画であり、岡本太郎の「芸術は爆発だ」と力んでみせる歌舞伎の見栄を切るようなパフォーマンスなのです。
この岡本太郎が反抗していたのは、実は日本の古典や近代化された日本画ではなくて、ピカソに代表されるヨーロッパの前衛美術であり、ピカソと岡本太郎の間にある反発と反抗の関係こそが、「日本の前衛」の構造なのです。
アフリカの黒人彫刻と縄文式土器という、ピカソと岡本太郎が同じように原始美術を肯定し、そこに大きなインスピレーションを受けて絵画を描いていています。しかしピカソの絵画、たとえば「アヴィニヨンの娘たち」は、モダンアートであって、しかも《オプティカル・イルージョン》の絵画であるのです。それに対して岡本太郎の絵画は、《ペンキ絵》であって、モダンアートではなくて、むしろ色つきの劇画というべき原始美術なのです。 ジャック・ラカンの用語を使えば、ピカソの「アヴィニヨンの娘たち」は《象徴界》の芸術ですが、岡本太郎の作品は《現実界》の作品と言えます。
敗戦後の日本の現代美術の中には、こうしたピカソをはじめとする欧米美術に刺激されつつ、これに反発して、より過激に反抗の身振りをする〈日本反文化の伝統〉を引き継ぐ《現実界》の《ペンキ絵》の美術が異常繁殖しています。こうした岡本太郎的な下品な色彩が、草間弥生の毒々しい花にも引き継がれているのです。彦坂尚嘉の私見では、これは芸術ではなくて、「ばさら」なのです。
2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(4) [アート論]
従来の銀座の貸し画廊を歩き回る画廊巡りや、美術館や博物館を一人でコツコツと歩いて、ベンチの隅でお弁当を密やかに食べるといった貧乏臭い美術愛好家を、あざ笑い、時代遅れにする、圧倒的なアート現象の社会的スペクタクル化がはかられたのです。
しかし、このことは、アートシーンで独自に起きたものではなくて、後期資本主義社会が生み出すスペクタクル化という疎外現象のアート版に過ぎないのです。
ギ・ドゥボールが『スペクタクルの社会』(1967年)で指摘した事は、多くの人々が受動的な観客の位置に押し込められた世界に、後期資本主義社会がなったということです。映画の観客のようにただ世界を眺めることしか残されていないという状態におかれたことをスペクタクル化と言い、これが資本主義の究極の統治形態だと言うのです。




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
しかし、高度消費社会の中で、資本主義そのものに対する根源的な否定意識も広がって来ています。なぜ私たちは、すべての事に対して消費者として受身でなければいけないのか? なるべくお金を使わないようにする事。ニューヨークでは、ホームレスでもない人々が、ゴミとして捨てられる食品をゴミ箱から拾って食べるまでされていると、ネットで読みました。自動車も持つ事を拒否する若者の増加。こうした高度消費社会に対する反撃の動きが次第に社会の底流に広がって行きます。
アートという自由と信じられていたものが、勝手にデザイン化に転化され、一部の新興成金により誤読され、誤読に誤読が重ねられ、幻影の時代の中で、根拠なき熱狂の嵐が吹き荒れ、美術市場は異様に高騰し、現代アートの裸の王様化が進んでいったのが2000年代でした。村上隆の作品もしかり、現代美術としてもてはやされる作品は精巧なデザインや下品さまでも上手に取り込み、さも高尚であるかのように私たちを取り巻いて、幻影と、誤読の罠をしかけてきているように感じます。
こうした村上隆的なキャラクター・アートという新・偶像崇拝美術に対する反撃であるかのように振る舞う形で、越後妻有トリエンナーレの北川フラムの里山に対する思いの思想は展開して行ったのですが、同時に農舞台やキョロロ、そしてキナーレという幻影の巨大建築が建設されていきました。

MVRDV (エムブイアールディーブイ) はオランダのロッテルダムを拠点とする建築家集団で、1991年に設立されものです。名前の由来は事務所設立時のメンバーの三人の頭文字からとったものであるのです。
- ヴィニー・マース(Winy Maas、1959年 - )
- ヤコブ・ファン・ライス(Jacob van Rijs、1964年 - )
- ナタリー・デ・フリイス(Nathalie de Vries、1965年 - )
ヴィニー・マースとヤコブ・ファン・ライスはレム・コールハースの主宰する建築設計事務所OMA(Office for Metropolitan Architecture)の出身です。
レム・コールハースは、1944年生まれのオランダの建築家。代表的な作品は、シアトル中央図書館(2004年)、カーサ・ダ・ムジカ (ポルトガル、ポルト、2004)などですが、私はこの両方を見に行っています。現在、中国中央電視台本部ビル (中国、北京、2004着工)が建設中です。

里山と自然と文化の魅力と不思議を楽しく展示する科学館という
コンセプトで建てられました。



村上隆の顔の《言語判定法》による分析 北川フラムの顔の《言語判定法》による分析
《第13次/喜劇領域》の《社会性の高いデザイン的人格》 《第6次元/自然領域》の《社会性の高いデザイン的人格》
《想像界》の人格 《想像界》の人格
彦坂尚嘉の《言語判定法》での分析で見るかぎり、二人とも社会性の高いデザイン的エンターテイメント的な人格なのです。そして《シリアス人間》で、しかも「真実の人」であるという共通性があります。アートのスペクタクル化が、実はアートのデザイン化であり、幻影化であり、それがアートの社会性の増大であったことと、この2人のカリスマの人格構造は一致していたのです。
2000年代というのは、こうして村上隆の時代であるとともに北川フラムの越後妻有トリエンナーレの時代であったのです。この二人の背後には1995年からのアメリカ社会の過剰消費の世界中への波及による『根拠なき熱狂』があり、そしてグローバリゼーションの中の自虐的で不快なセルフ・オリエンタリズムがあり、さらに日本の《大地》のアメリカゼーションがあったのです。
私自身は美術家として、この越後妻有トリエンナーレ第一回から全ての回に参加して、Floor Eventシリーズを4回展開してきただけに、感慨深くこの北川フラムによる10年間の魔術的な夢を振り返らざるをえません。
Floor Event/フロアイベントというのは、自らが立つ床そのものを直視すると言うコンセプトの作品だからです。日本の《大地》がアメリカ化したという事実を直視しなければならなかったのです。
2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(3)


越後妻有はあくまでも日本の田舎であって、現代美術を、この日本の現実に還元して行くという、そういうローカリゼーションの美術展なのです。それは同時に、現代美術の前提価値そのものを解体して行くと言う脱-構築運動であって、そのデ・コンストラクション性を評価する視点で見て行かないと、北川フラムというアートディレクターに対する正統な理解はできません。
ローカリゼーション (localization) というのは、情報技術においては、コンピュータ・ソフトウェアを、現地語の環境に適合させることを言います。
越後妻有トリエンナーレで、北川フラムがディレクターとしてやっている仕事は、欧米生まれの現代美術を日本語に翻訳し、さらに日本の田舎の現実に適応できるように、アートの質を修正したり、アートの個人性を消して社会性を強調したデザインワークに変質させたり(実例・カバコフの作品) 、アートの高度な質を低くしたり、アートの仕様や様式の変更をしたり、アートの価値観や目的の変更を仕掛けていると言う、アート・ローカリゼーションの実践なのです。
それは従来の芸術至上主義や、純粋芸術という価値観や、個人主義制作を解体して、組み直す作業になります。住民参加の制作による作品の展開は、この近代個人主義的制作の、解体再編運動であったのです。それは《現代美術》というものを、日本の田舎という生活世界に基礎づけて行くという、最終的な和物化/和風化運動であったのです。こうして現代美術の「現地語化」という仕事をしたのが北川フラムであって、その結果としていくつかの傑出したアートディレクション・アートが生まれました。


実例としては2003年の代表作家の一人であった彦坂尚嘉の場合には、本籍地変更を実行し、展示場所の田麦という山村に自らの本籍を移すという事をやっています。次の2006年の代表作家となった菊池歩の「こころの花」の制作が、現地への移住によって、その長期性の中で作られています。したがって、そのような作家の積極的な参加を引き起こすシステムを立ち上げ、作動させ得た北川フラムの豪腕は見事なものと評価するべきで、他の誰もマネの出来ない偉業であったと私は思います。
菊池歩の作品「こころの花-あの頃へ」は大きな評判にはなって、現地の人気は非常に高いものでありました。しかし彦坂尚嘉の芸術分析では低くて、《第8次元 宗教領域》のデザイン的エンターテイメント作品と判断します。しかも絶対零度の美術という、つまり原始美術でありまして、 芸術的には【B級芸術】であったのです。【註3】
こうして越後妻有トリエンナーレ『大地の芸術祭』で作り出された「妻有アート」とも言うべき住民参加型の作品様式は、手の込んだ手芸、あるいは工芸 とも言える作りと、奇妙に類似した構造の作品となって、しだいに固定化していきます。



そういう飽きの空気の中で、今回の、杉浦久子+杉浦友哉+昭和女子大学杉浦ゼミの「雪ノウチ」という作品は、このような住民参加型の美しい手芸性を持った「妻有アート」の中でも際立つ秀作でありました。
たいへんにフェニミンな美しさのあるデザイン作品であって、しかしフロイトがいう《退化性》という私的歴史性をもった芸術作品ではありませんが、《1流》の《ハイアート》性をもつデザイン作品であったのです。合法的表現であって、私的な表現性が見えなくて、社会的公的性だけで成立しているので、エンターテイメントではあります。そして、作品は実体的ですので、ここでもエンターテイメント作品です。【註5】だがしかし、杉浦久子の「雪ノウチ」において、彦坂尚嘉責任の芸術分析で見る限り、「シニフィアン(記号表現)/シニフィエ(記号内容)の同時表示」という今日的な表現の重層性が達成されている事は、非常に高く評価できる事です。この構造は、かつての古典芸術のシーニュ性が解体されてシニフィアン(記号表現)に還元されたモダンアートの限界を超える、情報化社会の芸術の新しいアート・クオリティと言えるものだからです。それは「シニフィアン(記号表現)/シニフィエ(記号内容)の同時表示」という構造が、決してかつてのシーニュの復活ではなくて、離婚した夫婦が、また一緒に同席して並んでいる様な、そうした非統合性において獲得される今日的なアート・クオリティだからです。
ここにおいて、「妻有アート」がマンネリの原始美術性から脱して、次の飛躍を遂げ得る地平が示されていると言えます。
2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(2)

決して主張しすぎない淡い青の色合いに作家の環境への調和の精神が感じられます。




2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(1) [アート論]

2000年代日本アート論
越後妻有トリエンナーレを巡って


G8市民メディアセンター札幌実行委員会に参加。
1.『越後妻有トリエンナーレの中の名品を求めて巡るツアー』

今回、参加者20人で3泊4日の『越後妻有トリエンナーレ『大地の芸術祭』の中の名品を求めて巡るツアー』を組織して、コディネートして来たので、そのツアーと、その前の下見の中で見た作品を、ご報告したいと思います。
今回の企画者の彦坂尚嘉自身が、2つの場所での作品を越後妻有トリエンナーレに出品しているので、自分自身の作品を見せるという我田引水の意図は、明確にあるのです。中立的な記事を読む事を求める読者には不快なことかもしれませんが、現実でありますので、事前にお断りをしておきます。
なおこのツアーは、アートスタディーズという勉強会と、建築系ラジオの共同主催のものです。建築史/建築評論家の五十嵐太郎、建築家の山田幸司、松田達などの建築系の人々と、彦坂尚嘉、飯田啓子、秋元珠江、田嶋奈保子などのアーティスト、そしてギャラリストの玉田俊雄(タマダプロジェクト主宰)、さらに美術研究者やコレクター、学生、さらに田邊寛子や、木村静のような街起こしなのど地域市民運動をやっている人々も参加しています。
『名品を求めて巡るツアー』と名付けているのは、今こそ、感覚を研ぎ澄まし、自分の身体や脳や、自らの人格と教養の蓄積をかけた全身で感じることが重要だからです。
世間一般やマスコミを通じて空気や風聞として押し出されてくるお仕着せのアートではなく、自らの判断基準をもったアートを体感する意味で、ここで紹介する作品と向かい合いました。
とは言っても、彦坂尚嘉が彦坂尚嘉の作品を紹介し、説明する記事の部分では、当然のように中立性を求める読者の不審や疑念を呼ぶ記事となりますので、批判的に読んでいただくことをお願い致します。私自身に対する正統な批判には、正面から誠実に向き合いたいと思います。
今回の越後妻有トリエンナーレ名品ツアーで見た作品の中で、秀作をあげるとすると、先ずに山本想太郎の建具を使ったフロアーイベントとも言うべき作品だろうと思います。
次に紹介する彦坂尚嘉の間伐材をつかったフロアイベントと、床にものを敷くということで良く似た作品構造なのです。
山本想太郎は、1966年生まれの建築家です。早稲田大学理工学研究科(建築専攻)修士課程修了して坂倉建築研究所を経て、独立して山本想太郎設計アトリエを主宰しています。
今村創平、南泰裕らとともに建築家ネットワーック・プロスペクターをつくって活動して、前回の2006年には、このプロスペクターの作品として「コンタクト/足湯プロジェ」を

今回は、グループではなくて、一人で制作した作品です。
タバコの葉を乾燥させる倉庫として使われていた建物の内部に、庭のように歩く空間を作っています。


《第1次元〜第31次元》の多次元的な《真性の芸術》
ただし《超次元》と《第41次元》が無い。
《想像界》《象徴界》《現実界》の3界をもつ重層的な表現
気体/液体/固体/絶対零度の4様態をもつ多層的な表現
《シリアス・アート》《ハイアート》
シニフィアン(記号表現)の美術、ただしシニフィエ(記号内容)性が無い。
《透視立体》【A級美術】
山本想太郎の越後妻有トリエンナーレへの取り組みは、
これだけではなくて「妻有田中文男文庫」(作品番号10 2009年作品)
さらに、「安堀雄文記念館」(作品番号10 2006年作品)
「再構築」(作品番号31 2006年作品)、
「名ヶ山写真館」(作品番号36 2006年作品)と、
全部で5つもあるのです。
この精力的な活動の熱意が背景になって、今回の傑作が生まれたと思います。

さて、この山本想太郎の作品に呼応するかのように、建築の床面を、
あたかも外部の庭であるかのように反転させて、廃屋を芸術作品に
変貌させたのが彦坂尚嘉のフロアイベント2009(作品番号22)でした。
彦坂尚嘉は1946年うまれの美術家で、1970年多摩美術大学油彩科中退。
1969年に多摩美術大学の学園紛争のバリケードの中の造型作家同盟展という美術展でデビューしたアーティストです。そのときに出品したフロアイベントとウッドペインティングを、40年後の現在も展開し続けて継続制作しているという作家です。
今回の越後妻有トリエンナーレでは、田麦(作品番号22)という山村の廃屋ではフロアイベントの作品を展示し、もう一つ手塚貴晴のリノベーションしたイタリア・レストラン「黎の家」(作品番号229)の方には、ウッドペインティングの小品を5点展示しています。



2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(1) [アート論]


2000年代日本アート論
越後妻有トリエンナーレを巡って


G8市民メディアセンター札幌実行委員会に参加。

1. 北川フラムのローカリゼーション
越後妻有はあくまでも日本の田舎であって、現代美術を、この日本の現実に還元して行くという、そういうローカリゼーションの美術展なのです。それは同時に、現代美術の前提価値そのものを解体して行くと言う脱-構築運動であって、そのデ・コンストラクション性を評価する視点で見て行かないと、北川フラムというアートディレクターに対する正統な理解はできません。
ローカリゼーション (localization) というのは、情報技術においては、コンピュータ・ソフトウェアを、現地語の環境に適合させることを言います。
越後妻有トリエンナーレで、北川フラムがディレクターとしてやっている仕事は、欧米生まれの現代美術を日本語に翻訳し、さらに日本の田舎の現実に適応できるように、アートの質を修正したり、アートの個人性を消して社会性を強調したデザインワークに変質させたり(実例・カバコフの作品) 、アートの高度な質を低くしたり、アートの仕様や様式の変更をしたり、アートの価値観や目的の変更を仕掛けていると言う、アート・ローカリゼーションの実践なのです。
それは従来の芸術至上主義や、純粋芸術という価値観や、個人主義制作を解体して、組み直す作業になります。住民参加の制作による作品の展開は、この近代個人主義的制作の、解体再編運動であったのです。それは《現代美術》というものを、日本の田舎という生活世界に基礎づけて行くという、最終的な和物化/和風化運動であったのです。こうして現代美術の「現地語化」という仕事をしたのが北川フラムであって、その結果としていくつかの傑出したアートディレクション・アートが生まれました。

実例としては2003年の代表作家の一人であった彦坂尚嘉の場合には、本籍地変更を実行し、展示場所の田麦という山村に自らの本籍を移すという事をやっています。次の2006年の代表作家となった菊池歩の「こころの花」の制作が、現地への移住によって、その長期性の中で作られています。したがって、そのような作家の積極的な参加を引き起こすシステムを立ち上げ、作動させ得た北川フラムの豪腕は見事なものと評価するべきで、他の誰もマネの出来ない偉業であったと私は思います。
菊池歩の作品は大きな評判にはなって、現地の人気は非常に高いものでありました。しかし彦坂尚嘉の芸術分析では低くて、《第8次元 宗教領域》のデザイン的エンターテイメント作品と判断します。しかも絶対零度の美術という、つまり原始美術でありまして、 芸術的には【B級芸術】であったのです。【註3】
こうして越後妻有トリエンナーレ『大地の芸術祭』で作り出された「妻有アート」とも言うべき住民参加型の作品様式は、手の込んだ手芸、あるいは工芸 とも言える作りと、奇妙に類似した構造の作品となって、しだいに固定化していきます。

そういう飽きの空気の中で、今回の、杉浦久子+杉浦友哉+昭和女子大学杉浦ゼミの「雪ノウチ」という作品は、このような住民参加型の美しい手芸性を持った「妻有アート」の中でも際立つ秀作でありました。
たいへんにフェニミンな美しさのあるデザイン作品であって、しかしフロイトがいう《退化性》という私的歴史性をもった芸術作品ではありませんが、《1流》の《ハイアート》性をもつデザイン作品であったのです。合法的表現であって、私的な表現性が見えなくて、社会的公的性だけで成立しているので、エンターテイメントではあります。そして、作品は実体的ですので、ここでもエンターテイメント作品です。【註5】だがしかし、杉浦久子の「雪ノウチ」において、彦坂尚嘉責任の芸術分析で見る限り、「シニフィアン(記号表現)/シニフィエ(記号内容)の同時表示」という今日的な表現の重層性が達成されている事は、非常に高く評価できる事です。この構造は、かつての古典芸術のシーニュ性が解体されてシニフィアン(記号表現)に還元されたモダンアートの限界を超える、情報化社会の芸術の新しいアート・クオリティと言えるものだからです。それは「シニフィアン(記号表現)/シニフィエ(記号内容)の同時表示」という構造が、決してかつてのシーニュの復活ではなくて、離婚した夫婦が、また一緒に同席して並んでいる様な、そうした非統合性において獲得される今日的なアート・クオリティだからです。
ここにおいて、「妻有アート」がマンネリの原始美術性から脱して、次の飛躍を遂げ得る地平が示されていると言えます。
artscape [日記]
2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(3)2-2 [アート論]
おそらくこうした調和への視点を逆転させる事で、この越後妻有トリエンナーレのかなりの部分は出来ているのです。つまり不調和にする事で成立していると見えるものが多いということです。その不調和が、芸術である故のなのか、それともデザイン的エンターテイメント作品であるゆえなのか?
日本文化には、《文明》対《原始世界》という、重要な対立構造が潜在しているのです。外国から高度の人工的な新文明が日本に入ってきて、それを輸入し喜んで学び、支配者たちはこの《輸入文明》、例えば仏教や、あるいは西洋文化を背景にして民衆を支配するのですが、支配される民衆の中には、文明以前の、狩猟採取文化、つまり野蛮な文化が脈々と流れていて、上級の《輸入文明》に対して、常に反抗的な姿勢があるというのです。しかし問題が複雑なのは、反抗的な姿勢が屈折していることです。反抗自体が《輸入文明》に触発され、反発しつつ、にもかかわらず模倣し、なぞりつつ解体し、伝統的な野蛮文化のボキャブラリーの中に還元し、あざ笑うことに表現を見いだしていくという、複雑な摂取と解体の流れがあり、「ばさら」とか「かぶく」とか言われる美意識となります。
「ばさら」「かぶく」という言葉を、辞書でひいてみると次のようにあります。
「ばさら【婆裟羅】室町時代の流行語。①遠慮なくふるまうこと。乱暴。 ②はでに飾り立てて、いばること。だて。③しどけなく乱れること」
「かぶく【傾く】①頭がかたむく。かしぐ。②はでで異様なふるまい・みなりをする。」(日本語大辞典 講談社 一九八九年)
つまり日本の中には乱暴で、はでに飾り立てて、しどけなく乱れる表現の系譜があるのですが、これが室町時代に「ばさら」とか「かぶく」というような言葉で姿をあらわし、それはしかし不自然なものであり、異様で、派手で、エキセントリックで、《異端の系譜》の源流とも言うべきものになるのです。
これを戦後日本美術の中で分かりやすく言えば、それは敗戦後の岡本太郎によって唱えられた縄文主義であり、対極主義であり、あのどぎつい派手な色合いの絵画であり、岡本太郎の「芸術は爆発だ」と力んでみせる歌舞伎の見栄を切るようなパフォーマンスなのです。
この岡本太郎が反抗していたのは、実は日本の古典や近代化された日本画ではなくて、ピカソに代表されるヨーロッパの前衛美術であり、ピカソと岡本太郎の間にある反発と反抗の関係こそが、「日本の前衛」の構造なのです。
アフリカの黒人彫刻と縄文式土器という、ピカソと岡本太郎が同じように原始美術を肯定し、そこに大きなインスピレーションを受けて絵画を描いていています。しかしピカソの絵画、たとえば「アヴィニヨンの娘たち」は、モダンアートであって、しかも《オプティカル・イルージョン》の絵画であるのです。それに対して岡本太郎の絵画は、《ペンキ絵》であって、モダンアートではなくて、むしろ色つきの劇画というべき原始美術なのです。 ジャック・ラカンの用語を使えば、ピカソの「アヴィニヨンの娘たち」は《象徴界》の芸術ですが、岡本太郎の作品は《現実界》の作品と言えます。
敗戦後の日本の現代美術の中には、こうしたピカソをはじめとする欧米美術に刺激されつつ、これに反発して、より過激に反抗の身振りをする〈日本反文化の伝統〉を引き継ぐ《現実界》の《ペンキ絵》の美術が異常繁殖しています。
『再考・近代日本の絵画』展(二〇〇四年、東京都現代美術館+東京藝術大学美術館)には、特に多く選ばれていたので、出品された作品の中で《現実界》の《ペンキ絵》の美術をピックアップすると、戦前・戦中には《現実界》の美術は一点もなくて、戦後には岡本太郎太郎作品以降次のようになります。
岡本太郎「森の掟」(一九五〇年)
河原温「孕んだ女」(一九五四年)
今井俊満「東方の光」(一九五七年)
堂本尚郎「絵画六〇ム二〇」(一九六〇年)
工藤哲巳「X型基本体に於ける増殖性連鎖反応」(一九六〇年)
荒川修作「Work A」「Work B」(一九六〇年)
草間弥生「パシフィック・オーシャン」(一九六〇年)
元永定正「作品」(一九六二年)
中村正義「男女」(一九六三年)
田中敦子「作品(たが)」(一九六三年)
篠原有志男「思考するマルセル・デュシャン」(一九六三年)
白髪一雄「無題(赤蟻王)」(一九六四年)
草間弥生「トラベリング・ライフ」(一九六四年)
菅井汲「夏のヴァカンス」(一九六五年)
工藤哲巳「あなたの肖像六七」(一九六七年)
大竹伸朗「家系図」(一九八六ム八八)
山本富章「Untiled」(一九八七)
加納光於「繁み・運動・エレメントD」(一九八八年)
森村泰昌「美術史の娘『王女B』」(一九八九年)
岡崎乾二郎「(左)平面ばかり・・・」(二〇〇一年)
中村一美「死を悼みて濡れた紫の水際に立つ者」(二〇〇一ム〇二)
こういうリストアップをすると、〈日本反文化の伝統〉を引き継ぐ《現実界》の《ペンキ絵》の美術が、いかに敗戦後の日本の現代美術を代表しているかが理解できます。繰り返しますと、こういう原始美術は、戦前には描かれていないのです。敗戦によって、日本の文化が原始的で野蛮なものに退化したと、私は考えます。
こうした岡本太郎的な下品な色彩が、草間弥生の毒々しい花にも引き継がれているのです。彦坂尚嘉の私見では、これは芸術ではなくて、「ばさら」なのです。
2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(2)
従来の銀座の貸し画廊を歩き回る画廊巡りや、美術館や博物館を一人でコツコツと歩いて、ベンチの隅でお弁当を密やかに食べるといった貧乏臭い美術愛好家を、あざ笑い、時代遅れにする、圧倒的なアート現象の社会的スペクタクル化がはかられたのです。
しかし、このことは、アートシーンで独自に起きたものではなくて、後期資本主義社会が生み出すスペクタクル化という疎外現象のアート版に過ぎないのです。
ギ・ドゥボールが『スペクタクルの社会』(1967年)で指摘した事は、多くの人々が受動的な観客の位置に押し込められた世界に、後期資本主義社会がなったということです。映画の観客のようにただ世界を眺めることしか残されていないという状態におかれたことをスペクタクル化と言い、これが資本主義の究極の統治形態だと言うのです。




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
しかし、高度消費社会の中で、資本主義そのものに対する根源的な否定意識も広がって来ています。なぜ私たちは、すべての事に対して消費者として受身でなければいけないのか? なるべくお金を使わないようにする事。ニューヨークでは、ホームレスでもない人々が、ゴミとして捨てられる食品をゴミ箱から拾って食べるまでされていると、ネットで読みました。自動車も持つ事を拒否する若者の増加。こうした高度消費社会に対する反撃の動きが次第に社会の底流に広がって行きます。
アートという自由と信じられていたものが、勝手にデザイン化に転化され、一部の新興成金により誤読され、誤読に誤読が重ねられ、幻影の時代の中で、根拠なき熱狂の嵐が吹き荒れ、美術市場は異様に高騰し、現代アートの裸の王様化が進んでいったのが2000年代でした。村上隆の作品もしかり、現代美術としてもてはやされる作品は精巧なデザインや下品さまでも上手に取り込み、さも高尚であるかのように私たちを取り巻いて、幻影と、誤読の罠をしかけてきているように感じます。
こうした村上隆的なキャラクター・アートという新・偶像崇拝美術に対する反撃であるかのように振る舞う形で、越後妻有トリエンナーレの北川フラムの里山に対する思いの思想は展開して行ったのですが、同時に農舞台やキョロロ、そしてキナーレという幻影の巨大建築が建設されていきました。

MVRDV (エムブイアールディーブイ) はオランダのロッテルダムを拠点とする建築家集団で、1991年に設立されものです。名前の由来は事務所設立時のメンバーの三人の頭文字からとったものであるのです。
- ヴィニー・マース(Winy Maas、1959年 - )
- ヤコブ・ファン・ライス(Jacob van Rijs、1964年 - )
- ナタリー・デ・フリイス(Nathalie de Vries、1965年 - )
ヴィニー・マースとヤコブ・ファン・ライスはレム・コールハースの主宰する建築設計事務所OMA(Office for Metropolitan Architecture)の出身です。
レム・コールハースは、1944年生まれのオランダの建築家。代表的な作品は、シアトル中央図書館(2004年)、カーサ・ダ・ムジカ (ポルトガル、ポルト、2004)などですが、私はこの両方を見に行っています。現在、中国中央電視台本部ビル (中国、北京、2004着工)が建設中です。

里山と自然と文化の魅力と不思議を楽しく展示する科学館という
コンセプトで建てられました。



村上隆の顔の《言語判定法》による分析 北川フラムの顔の《言語判定法》による分析
《第13次/喜劇領域》の《社会性の高いデザイン的人格》 《第6次元/自然領域》の《社会性の高いデザイン的人格》
《想像界》の人格 《想像界》の人格
彦坂尚嘉の《言語判定法》での分析で見るかぎり、二人とも社会性の高いデザイン的エンターテイメント的な人格なのです。そして《シリアス人間》で、しかも「真実の人」であるという共通性があります。アートのスペクタクル化が、実はアートのデザイン化であり、幻影化であり、それがアートの社会性の増大であったことと、この2人のカリスマの人格構造は一致していたのです。
2000年代というのは、こうして村上隆の時代であるとともに北川フラムの越後妻有トリエンナーレの時代であったのです。この二人の背後には1995年からのアメリカ社会の過剰消費の世界中への波及による『根拠なき熱狂』があり、そしてグローバリゼーションの中の自虐的で不快なセルフ・オリエンタリズムがあり、さらに日本の《大地》のアメリカゼーションがあったのです。
私自身は美術家として、この越後妻有トリエンナーレ第一回から全ての回に参加して、Floor Eventシリーズを4回展開してきただけに、感慨深くこの北川フラムによる10年間の魔術的な夢を振り返らざるをえません。
Floor Event/フロアイベントというのは、自らが立つ床そのものを直視すると言うコンセプトの作品だからです。日本の《大地》がアメリカ化したという事実を直視しなければならなかったのです。