佐々木薫/超1流の《無芸術》と宗達なるもの [アート論]
佐々木薫という作家は、1980年代の超少女と言われる《無芸術》時代様式を、ある意味で集約して《超1流》の作品に結実したアーティストです。
その最初は、多摩美術大学での1981年制作の具象画ですが、指導教授は宮崎進で、ここでもすでに固有性のある《一流》絵画で《芸術》作品を描いています。その後エリザベス・マーレーの影響を思わせる生け花の様な彩色された樹木作品を作りますが、ここですでに《超1流》の良い作品になっていますが、それは手芸性や装飾性を持つ《無芸術》と言うべき秀作です。《無芸術》の作品というのは、美術史上にはいくつもりますが、宗達やアンリールソー、そしてマティスなどの作品です。そこでは官能性に対する大脳皮質的な抑圧が無くて、官能に対して肯定的な美術なのです。
1986年前後から木枠に張らないキャンバス地の上に中国紙を貼って整形した、有機的なフォルムの外形をもつシェエイブドキャンバスの大型のレリーフ作品を連作して行きます。これらも《無芸術》で、この時代の超少女とか、工作少女といわれた時代の表現様式と質を、高度な《超1流》の作品にまで高めて、しかも現在も保存しています。多くの作品が《6流》で、しかも保存されているものが少ない中で、注目すべき作家なのです。

しかし1989年からの作品は、視覚的には類似していますが《反芸術》作品に変貌して1995年まで制作されます。2000年代になると、白いインスタレーションに大幅にスタイルを変えるのですが、そこでは大脳皮質的な抑圧の精神が作動していて《芸術》作品になっています。つまり初期の1981年に《芸術》作品から出発して、《無芸術》作品で1980年代美術の結晶化した作品を作りながらも、《反芸術》に移行して、最後に再び《芸術》作品に回帰しているのです。こうした1980年代の美術作品の変貌は、アメリカの画家テリー・ウインタースにも見られるもので、1980年代という時代の変動性を体現したものだからだと思います。
回顧してみれば、1980年代様式を結実した宗達的とも言える《超1流》の《無芸術》作品が印象にのこるものであり、歴史的に意味のある作品だと思います。この展開を計るには、しかし《無芸術》だけでは無理で、ジェフクーンズに見られるように《無芸術》《非芸術》《反芸術》《芸術》の4つを統合した、高度に複雑な作品形成に向かうべきなのです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
アート・スタディーズ
『第16回アート・スタディーズ 』へのお誘いです。
11月2日(月)午後6時から京橋のINAX:GINZAです。
1980年代は、ニューウエイブ台頭の時代でした。これは
再度、1995年〜2008年の過剰消費の中で
繰り返されたのではないでしょうか。
ディレクター・彦坂尚嘉
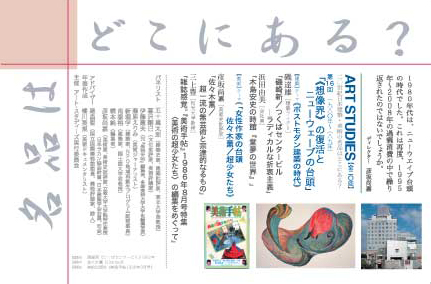
======================================================
レクチャー&シンポジウム
20世紀日本建築・美術の名品はどこにある?
第16回アート・スタディーズ
1980年〜1989年「《想像界》の復活とニューウェーブの台頭」
ゲスト講師
【建築】テーマ ポストモダン建築の時代(仮題)
講師 磯 達雄 (建築ライター)
サブテーマ「磯崎新/つくばセンタービル−ラディカルな折衷主義」
講師 浜田 由美(会社員)
サブテーマ「木島安史の時館『堂夢の世界』」
【美術】テーマ 《女性作家の台頭 佐々木薫/超少女たち》
講師 松永 康(アート・コーディネーター)
サブテーマ
「佐々木薫と名品−共時的な視点から」
講師
三上 豊(和光大学教授)
サブテーマ 「雑誌感覚。『美術手帳』1986年8月号特集
〈美術の超少女たち〉の編集をめぐって」

『アート・スタディーズ』とは?
アート・スタディーズは多くの人の鑑賞に資する、歴史に記録
すべき《名品》を求め、20世紀日本の建築と美術を総括的、通
史的に検証、発掘する始めての試みです。先人が残してくれた
優れた芸術文化を、多くの世代の人々に楽しんで頂けるよう、
グローバルな新たな時代にふさわしい内容でレクチャー、討議いたします。
いたします。
◆ディレクター
彦坂尚嘉(美術家、日本ラカン協会会員、立教大学大学院特任教授)
◆プロデューサー
五十嵐太郎(建築史家、建築批評家、東北大学教授)
◆アドバイザー
建畠晢(美術批評家、国立国際美術館館長)
◆討議パネリスト
◇五十嵐太郎(建築史、建築批評、東北大学教授)
◇伊藤憲夫(元『美術手帖』編集長、多摩美術大学大学史編纂室長)
◇暮沢剛巳(文化批評、美術評論家)
◇新堀 学(建築家、NPO地域再創生プログラム副理事長)
◇橋本純(編集者)
◇藤原えりみ(美術ジャーナリスト)
◇南泰裕(建築家、国士舘大学准教授)
◆司会
彦坂尚嘉(アート・スタディーズ ディレクター)
◆年表作成
橘川英規(美術ドキュメンタリスト)
◆日時:2009年11月2日(月)
17:30開場、18:00開始、21:00終了、終了後懇親会(別会場)
(東京都中央区京橋3−6−18/地下鉄銀座線京橋駅2番出口徒歩2分)
(当日連絡先は 090-1212−4415 伊東)
◆定員:60名(申込み先着順)
◆参加費:500円(懇親会参加費は別途)
◆お申し込み・お問い合わせは
氏名、住所、所属、連絡先、予約人数を明記の上、下記e-mailアドレスへ
詳細情報はこちら
HYPERLINK "http://artstudy.exblog.jp/" http://artstudy.exblog.jp/
◆主催 アート・スタディーズ実行委員会
◆共催 リノベーション・スタディーズ委員会
◆後援 毎日新聞社
日本建築学会
日本美術情報センター
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆「アート・スタディーズ」の詳細及びこれまでの情報
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

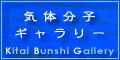
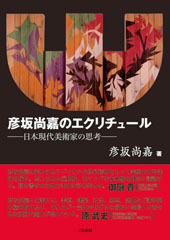
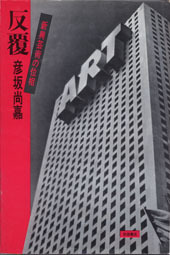

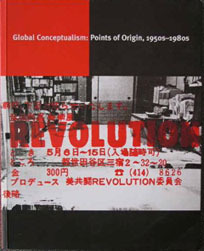



こんにちは。
8次元や41次元などの言葉の意味が分かりません。それらの意味と、それらの言葉を使う根拠を教えてください。
by オオクラ (2009-10-27 03:32)
このブログの批評的な側面は文章が面白く好きなのですがどうも取り上げる作家がイケてない人が多いようです。この作品もストレッチャがないのでスポールシュルファス(懐かしい?)を連想させますし先日の泡の風景写真も理屈としては分かりますが写真以外ではないと・・・・・
競馬の予想屋というと失礼ですがもう少し未来に脚光浴びる作家さんを取り上げてほしいです。
無理な注文で済みませんです。
by みどり (2009-10-28 02:04)
オオクラ様
一度お返事を書いたのですが、うまくアップできなくて、消えてしまって、お返事遅れました。本編で1本まとめてお答えします。
みどり様
未来に脚光を浴びる作家さんというのが、たぶん、みどりさんの考える作家と私のものは違うのでしょう。
泡の斉藤ちさとさんは、来年春の新国立美術館の展覧会が決まりました。
佐々木薫さんは、あくまでも1980年代の美術史的な回顧で、無視されていた存在を取り上げています。彼女の作品をスーポルシュルファスというのは、違います。そもそも1960年代末のフランスのスーポルシュルファスそのものが、不毛なものでしたが、それらの作品とは、1975年以降のいわゆるニューウエーブ的な表現はまったく違います。
私のブログでは、不十分ながらもいろいろな作家を取り上げていますので、読んでみて下さい。
あと、何か取り上げて欲しい作家がいれば、教えて下さい。ネットで画像が取れるものであれば、出来るだけ書くつもりです。
by ヒコ (2009-10-28 05:31)