2000年代日本現代アート論 越後妻有トリエンナーレを巡って(5)
おそらくこうしたオーソドックスな調和への視点を逆転させる事で、この越後妻有トリエンナーレのかなりの部分は出来ているのです。つまり調和を避けて、不調和にする事で、芸術という名前は成立していると見えるものが多いということです。不調和にする一つの方法が、ボルタンスキーに見られる廃墟性や、崩壊性です。廃墟や崩壊が、人を引きつけるのは、確かなのですが、しかし崩壊が芸術であるとは言えないのです。もう一つは「ばさら」です。
まず、廃墟性や崩壊性についてみてみましょう。
今回の目玉作家の塩田千晴の作品です。
不調和性というのは、芸術であることを、根拠づけるものなのか?
越後妻有トリエンナーレの目玉の作品のとんど全部はデザイン的エンターテイメント作品であって、私には《真性の芸術》として評価することができません。長谷川裕子が言うように『アートとデザインの遺伝子を組み替える』ことが実際に行われていて、これらの目玉作品の社会的デザイン性が高い事は充分に認めますが、《真性の芸術》性は欠けているのです。

日本文化には、《文明》対《原始世界》という、重要な対立構造が潜在しているのです。外国から高度の人工的な新文明が日本に入ってきて、それを輸入し喜んで学び、支配者たちはこの《輸入文明》、例えば仏教や、あるいは西洋文化を背景にして民衆を支配するのですが、支配される民衆の中には、文明以前の、狩猟採取文化、つまり野蛮な文化が脈々と流れていて、上級の《輸入文明》に対して、常に反抗的な姿勢があるというのです。しかし問題が複雑なのは、反抗的な姿勢が屈折していることです。反抗自体が《輸入文明》に触発され、反発しつつ、にもかかわらず模倣し、なぞりつつ解体し、伝統的な野蛮文化のボキャブラリーの中に還元し、あざ笑うことに表現を見いだしていくという、複雑な摂取と解体の流れがあり、「ばさら」とか「かぶく」とか言われる美意識となります。
「ばさら」「かぶく」という言葉を、辞書でひいてみると次のようにあります。
「ばさら【婆裟羅】室町時代の流行語。①遠慮なくふるまうこと。乱暴。 ②はでに飾り立てて、いばること。だて。③しどけなく乱れること」
「かぶく【傾く】①頭がかたむく。かしぐ。②はでで異様なふるまい・みなりをする。」(日本語大辞典 講談社 1989年)
つまり日本の中には乱暴で、はでに飾り立てて、しどけなく乱れる表現の系譜があるのですが、これが室町時代に「ばさら」とか「かぶく」というような言葉で姿をあらわし、それはしかし不自然なものであり、異様で、派手で、エキセントリックで、《異端の系譜》の源流とも言うべきものになるのです。
これを戦後日本美術に当てはめて、分かりやすく言えば、それは敗戦後の岡本太郎によって唱えられた縄文主義であり、対極主義であり、あのどぎつい派手な色合いの絵画であり、岡本太郎の「芸術は爆発だ」と力んでみせる歌舞伎の見栄を切るようなパフォーマンスなのです。
この岡本太郎が反抗していたのは、実は日本の古典や近代化された日本画ではなくて、ピカソに代表されるヨーロッパの前衛美術であり、ピカソと岡本太郎の間にある反発と反抗の関係こそが、「日本の前衛」の構造なのです。
アフリカの黒人彫刻と縄文式土器という、ピカソと岡本太郎が同じように原始美術を肯定し、そこに大きなインスピレーションを受けて絵画を描いていています。しかしピカソの絵画、たとえば「アヴィニヨンの娘たち」は、モダンアートであって、しかも《オプティカル・イルージョン》の絵画であるのです。それに対して岡本太郎の絵画は、《ペンキ絵》であって、モダンアートではなくて、むしろ色つきの劇画というべき原始美術なのです。 ジャック・ラカンの用語を使えば、ピカソの「アヴィニヨンの娘たち」は《象徴界》の芸術ですが、岡本太郎の作品は《現実界》の作品と言えます。
敗戦後の日本の現代美術の中には、こうしたピカソをはじめとする欧米美術に刺激されつつ、これに反発して、より過激に反抗の身振りをする〈日本反文化の伝統〉を引き継ぐ《現実界》の《ペンキ絵》の美術が異常繁殖しています。こうした岡本太郎的な下品な色彩が、草間弥生の毒々しい花にも引き継がれているのです。彦坂尚嘉の私見では、これは芸術ではなくて、「ばさら」なのです。





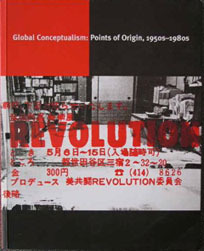



コメント 0